【2006年 第1回】相続件数を知ってどうするの? 相続
太田 潔(オオタ キヨシ)⇒ プロフィール

この「コラム」を引き受けるにあたって、「FPとしての視点に拘ることはないよ」との言葉をいただいたので、すべて恣意的解釈で述べていきたいと思います。
今回のタイトルとして『相続件数』を与えていただきましたが、関西流のお笑いで譬えると、「これを知ったところで何の役にたつの?」とツッコミたくなってしまうのですが・・・。(笑)
相続件数とは
一般人からすれば「相続件数」は?
と、聞かれたら、おそらくお亡くなりになった人の数であると答えるでしょう。
しかし、FPの視点から考えると、その対象になる言葉は「相続税の申告件数」を指すものと容易に判断できます。
もう少し平たく考えると、FPでも税理士資格者しか税務申告できないわけですから、「相続相談件数」と考えても決して間違っているとは言えないですね。
「死亡件数」と「課税件数」
参考までに、全国の「死亡件数」と「課税件数」を統計ベースに見ると、
死亡件数(A) 単位:人 課税件数(B) 単位:人 (B)÷(A) %
92年 (A):856,643 (B):54,449 (B)÷(A) :6.4%
95年 (A):922,139 (B):50,729 (B)÷(A) :5.5%
00年 (A):961,653 (B):48,463 (B)÷(A) :5.0%
02年 (A):978,379 (B):44,370 (B)÷(A) :4.5%
*国税庁、統計資料より。
ここから分かることは、高齢化率の上昇が死亡件数に反映されているようですが、路線価の下落が逆に課税対象者を減らしている側面もみられます。
相談者やその家族には税額以外に、もっと「情緒的」なものが隠されているのです。
この点で、冒頭に述べた「相続件数を知ってどうなるの?」と問い掛けたいのです。
【2006年07月25日00時00分】








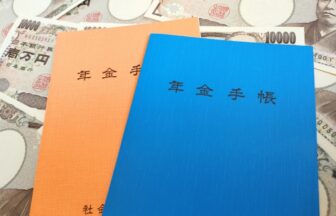
この記事へのコメントはありません。