マイアドバイザー® 顧問 岡本英夫 (オカモト ヒデオ)さん による月1回の連載コラムです。
ファイナンシャル・アドバイザー(近代セールス社;2022年春号以降休刊)の初代編集長として、同誌でも寄稿されていたエッセイの続編的な意味合いのあるコラムとなります。
今回は第29回目です。
岡本 英夫 ⇒ プロフィール
働けなくなったがん罹患者からの相談で多いのは医療費と生活費の確保をどうするかである。高額療養費と傷病手当金がすぐに思い浮ぶが、意外と知られていないのが、がんにより身体機能が落ち生活や労働に支障が出ている場合、障害年金を受給できる可能性が高いことである。今回は、障害年金の手続きのうち、初診日証明について紹介してみたい。
初診日証明要件の緩和
障害年金を受給するためには、①資格要件、②程度要件、③給付要件の3要件を満たす必要がある。この要件の1つでも欠けると、どんな重い障害でも障害年金を受給することはできない。この中でもっとも厄介なのが①の初診日において年金制度に加入していることの証明である。
初診日とは、障害の原因となる病気やけがで、初めて医師や歯科医師などの診察を受けた日であるが、発症から長い年月を経過した後に障害年金を請求することになった場合には、医院が廃業していたり、カルテが保存されていないなどの理由で初診日の証明が困難で、結果として年金が受け取れない場合があり、問題視されていた。
ところが、2015年10月から、初診日を証明するための要件が一部緩和され、過去に従来の方法で審査されたために不支給となっていたものについても、再申請されたときには新しい認定基準に基づいて再審査されることになった。具体的には、カルテ以外に「本人の申し立てに基づく医療機関が作成した資料」でも証明できるようになった。
カルテの保存期間は5年
カルテの保存期間は5年と定められているため、5年を経過した場合の初診日認定が困難になるケースが多い。それが、カルテが残っていなくても、5年以上前に医療機関が作成した資料に、本人が申し立てた診療日が記載されている場合には、初診日を認める取り扱いとなったのである。
また、医療機関による資料の作成が、請求の相当程度前である場合にも、初診日を認める取り扱いとした。これは障害年金をもらうために虚偽の初診日を医師に対して申告するとは考えられないためである。実は、これらの証明方法はすでに実施されてはいたが、公に認められていなかった。それを周知徹底したのが2015年10月だったのである。
その時に例示された資料は次のとおり。
・さかのぼれる一番古いカルテに基づく医師の証明 ・事業所の健康診断の記録
・発行日や診療記録等が確認できる診察券 ・健康保険の給付記録
・身体障害者手帳作成時の診断書 ・交通事故証明書 ・入院記録および診察受付簿
・労災の事故証明書 など
記憶に残る難病認定患者の初診日証明
2015年当時、筆者はがんと暮らしを考える会の社会保険労務士とともに食物アレルギーによる難病認定者からの障害年金の手続きの相談を受けていた。食物アレルギーの初診日を聞くと昭和の時代であり、医療機関はすでに廃業しカルテも残っていなかった。ところが、その難病認定者は、数十年前の紙の診察券を保管していたのである。
相談者から、診察券を見せられたとき、その診察券には医療機関名とともに、相談者の氏名と年齢、初診日が記載されていた。一緒に相談に対応していた社会保険労務士は「これで大丈夫です!」と小躍りし、当時の厚生年金加入を証明し、その後の障害年金の受給申請手続きを終えたのである。
この相談者は難病患者で、がん罹患者ではなかったが、大学病院の掲示板で「就労と家計の個別相談会」のチラシを見てがん相談支援センターに相談、事前予約をされていた。がんと暮らしを考える会では、病院から要請があれば、がん罹患者とその家族以外の相談にも対応していた。まれなケースだが記憶に残る相談事例である。




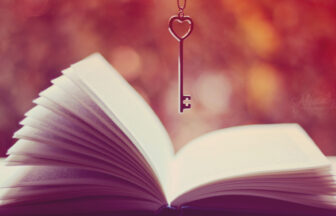




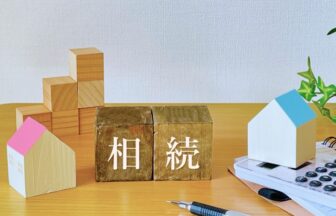
この記事へのコメントはありません。